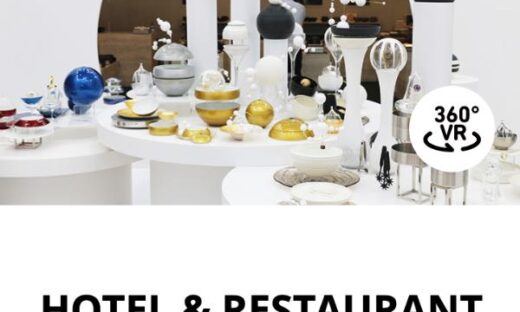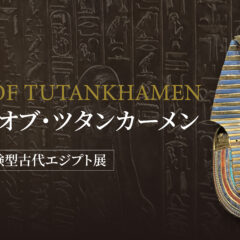初めての歌舞伎鑑賞で出会った“本物の迫力”

こんにちは。中畑です。
先月、人生で初めて歌舞伎座を訪れました。
観たのは「猿若祭二月大歌舞伎 昼の部」の『きらら浮世伝』。
以前から歌舞伎には興味があったのですが、なかなか行く機会がなく、実際に足を運んでみて、その世界の深さと面白さにすっかり魅了されてしまいました!
観劇のきっかけは、仕事を通じて蔦屋重三郎という人物に触れたことです。弊社は展示会やイベント、商業施設の空間づくりを手がけていますが、今回「台東区大河ドラマ館外装等整備業務委託」のプロポーザルに、グループ企業3社で参加し、無事受託することができました。その業務の一環として準備・整備を行ったのが、「べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館」の共用部の装飾です。
テーマは、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
準備を進める中で、蔦屋重三郎という人物の生き様や功績に自然と惹かれていきました。
そんな折、歌舞伎座で『きらら浮世伝』が上演されると知り、「これは観に行くしかない!」と即決。歌舞伎は敷居が高い印象もありましたが、実際に足を運んでみると、その印象はすっかり覆されました。
そしてなんと、座席は1階、花道のすぐ横という絶好の場所。役者さんが通るたびに空気が動き、所作や声の響き、視線の力強さまでもが肌に感じられました。
物語は蔦屋重三郎と、彼に関わる浮世絵師たちの姿を描いたもの。江戸の町の賑わいが舞台いっぱいに広がり、華やかな衣装と美術、緻密に計算された照明演出が相まって、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのようでした。
私自身、舞台づくりに携わる仕事をしていることもあり、つい照明の当て方や転換のスムーズさなど、舞台の裏側にも目が行ってしまいます。ですが、そのどれもが高い完成度で、まさに「匠の技」と言えるものでした。
何より印象に残ったのは、役者さんたちの表現力。セリフの一言一言に魂が込められ、目線ひとつで心情が伝わってくる。あれだけの演技を日々続けるとなると、もし風邪や花粉症だったらどうなるのだろう…などと考えてしまいましたが、それでも舞台に立ち続ける姿にプロとしての覚悟を感じました。
大河ドラマも歌舞伎も、蔦屋重三郎という人物を描いてはいますが、切り口も表現もまったく異なります。それぞれに良さがあり、どちらもその時代を生きた人々のエネルギーを伝えてくれます。
今回の観劇は、歌舞伎という伝統芸能の魅力を初めて実感する、貴重な体験でした。思っていた以上に親しみやすく、そして深く、美しい世界。気づけば次に観たい演目を探している自分がいて、また人生の楽しみがひとつ増えたような気がします。
そして、私たちが整備を担当した「べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館」は、現在、台東区民会館で2026年1月12日(月・祝)まで開催されています。蔦屋重三郎の生涯を中心に、江戸の文化や出版、浮世絵にまつわる貴重な資料や展示が揃っており、大河ドラマや歌舞伎をご覧になった方には、より深くその世界観を感じていただける内容になっています。
このブログを読んでくださった皆さまにも、ぜひ足を運んでいただき、江戸の魅力、蔦屋重三郎の生きた時代を体感していただけたら嬉しいです。